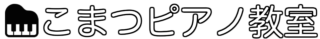三重県菰野(こもの)町に菰野ピアノ歴史館があります。
「こも」とは草の一種、昔たくさん生えていたのでこの地名になったそうです。
名古屋から近鉄四日市に行き、湯の山線に乗り換えて30分。東京からは行きにくい場所ですが、ちょうど近くの用事と重なって、春うららの好日に訪れることができました。
ここには調律師・岩田光義さんの収集した古楽器ピアノが、ところ狭しと並べられています。
たまたま奥のホールで開催されていた、地元の学校の聖歌隊によるコンサートの取材で、NHKの撮影クルーが来場していたため、小心者の私は避けるように開演中にささっと古楽器ピアノを弾き比べしました。
①スクエア型フォルテピアノ(1700年代)
憧れのフォルテピアノでしたが、修復調整中だったため、壊れたピアノといった音色。タッチが不揃いで出ない音もあり、素人には太刀打ちできませんでした。
②プレイエル ピアニーノ アップライト(1865年製)
ショパンの1845年の作品を少し弾いて、当時の雰囲気を味わうことができました。家のピアノのタッチと違い不揃いで、ミスタッチ連発‥
③ハインツマン グランド型(1882年製)
かなり弾きやすくなっていました。明治時代の日本人留学生は、こんなピアノを弾いていたのでしょうか。
④ダンハム&サン スクエア型(1903年製)
明治36年、モダンピアノに近く、しっかりしたタッチで音も伸びました。
残念だったのは試弾できるのが1人3台、1台3分までという規則があったこと。弾いてみたい楽器のほとんどが試弾不可だったこと。来館者が増え、古楽器の状態を維持するためには仕方のないことでしょう。
でもこのような所が注目されるようになったのは、良いことだと思います。だってショパンの時代の楽器は、今のピアノに比べると華奢で、音色も違っていたのですから。私も当時の曲を当時の音色で再現してみたいと思ったのです。
という訳で、普段は博物館でしか見ることができない古楽器に、直接触れて音を出せる、とても貴重な体験ができました。
さっそくうちの調律師に「年を取ったら鍵盤の重いピアノから、小さくて鍵盤の軽い古楽器に替えるというのはどうでしょうね。」と話したところ、「弾くたびに自分で調律しなければならない古楽器はメンテナンスが大変で、もう見たくもない。」という気分になるとのことでした(笑)。
確かに今のピアノは弾きやすくて音も狂いにくく、よく改良されていると実感です。